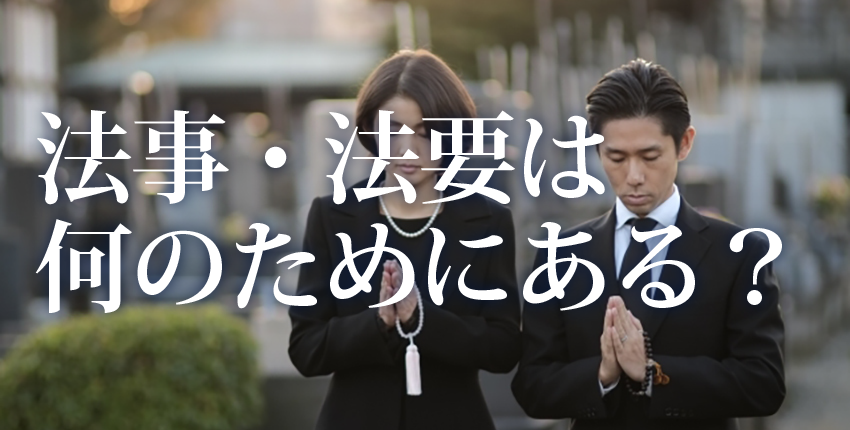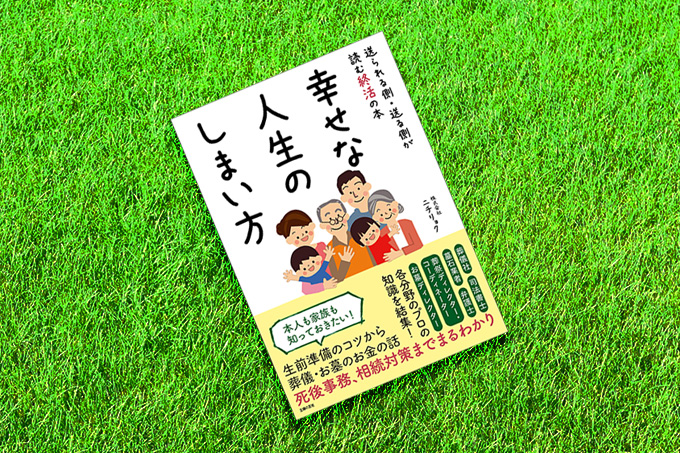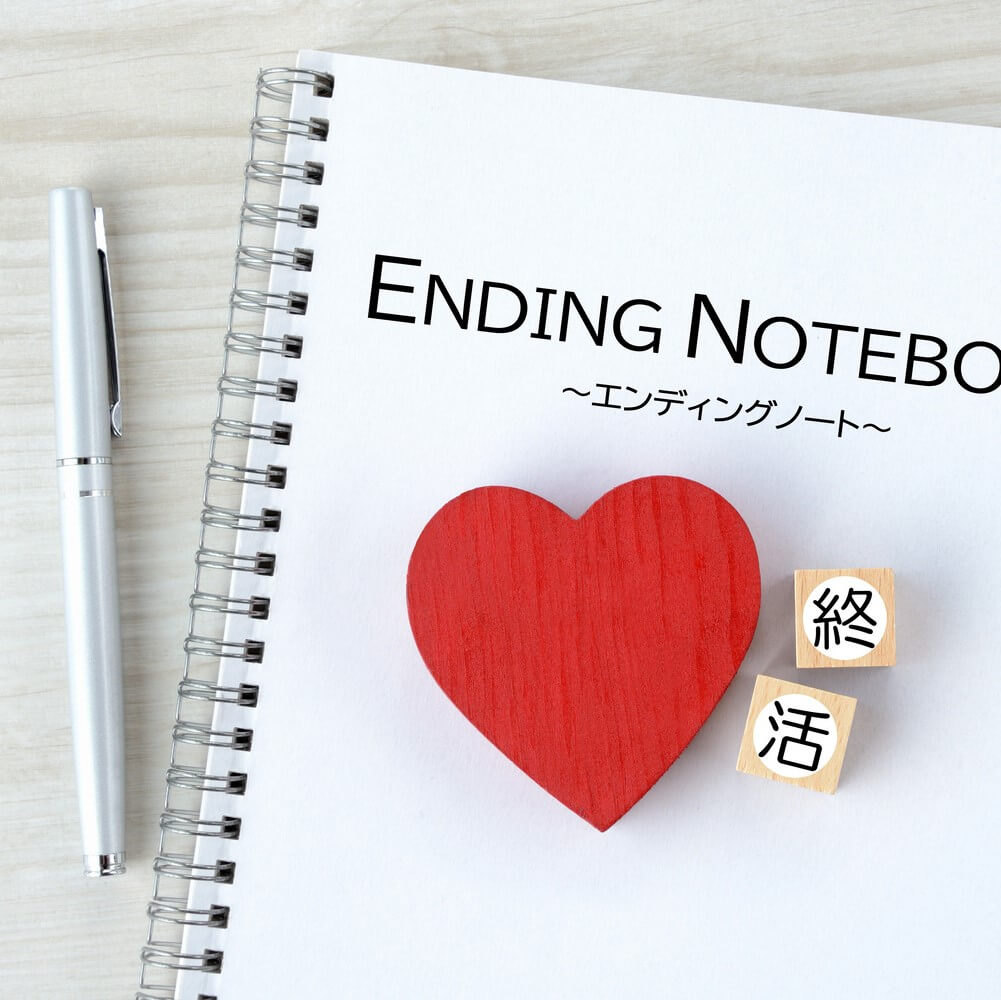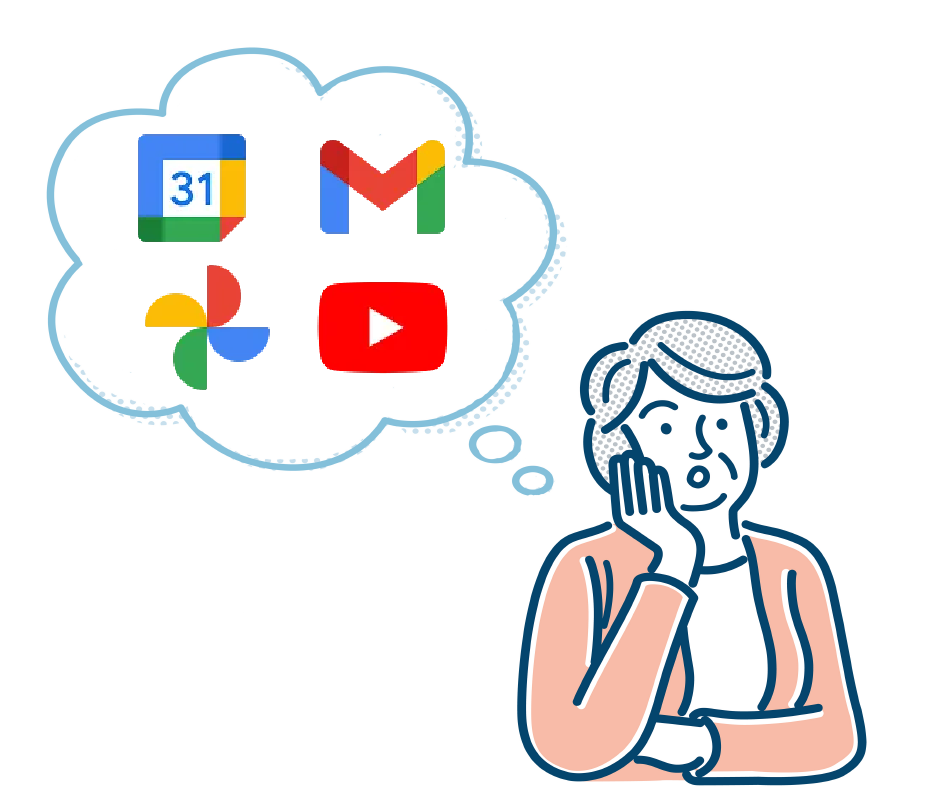【2026年度版】墓じまいや仏壇の処分の前に欠かせない閉眼供養:意味・対象・流れ・費用について解説
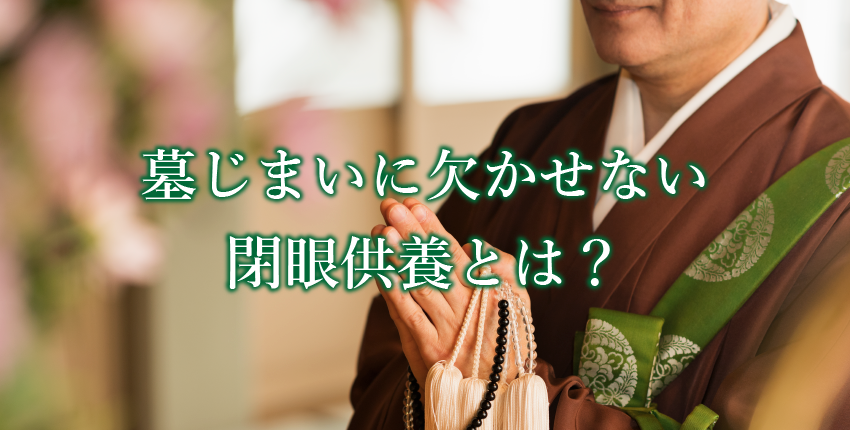
近年、お墓や仏壇を守っていた人が亡くなり、それらを後に残る人が引き継ぐことになったり、改葬(墓じまい)や仏壇・位牌の買い替え等を行う方が増えています。
その際に、必ず執り行わなければならないのが閉眼供養です。この記事では、閉眼供養についてご紹介します。
1.閉眼供養の持つ意味
仏教では、お墓や仏壇、仏像に仏様やご先祖様の魂を入れる開眼供養を行うことで、お墓や仏壇が礼拝の対象となります。
一方、それらを処分する場合には、お墓や本尊、ご位牌に宿っている仏様やご先祖様の魂を抜き、ただの石柱、モノに戻す必要があります。
そのために行う法要が閉眼供養です。
閉眼供養を行わずにお墓や仏壇・仏具を処分することは、礼拝対象を処分することに等しいので、避けなければなりません。
閉眼供養が行われていないお墓は撤去を断られることもあります。
ただし、浄土真宗では魂の概念がなく、故人はすぐに成仏するとされています。仏となった方の魂が現世に残る、霊として現れるという考えは浄土真宗の教えにそぐわないので閉眼法要は行われませんが、改葬(墓じまい)や仏壇の買い替え等をした場合には、仏様を移動するための儀式「遷座法要」を執り行います。
神道においても、お墓には魂が宿っていると考えられているため、改葬(墓じまい)の際には、いったんお墓から退いていただくための魂抜きのお祓いを行います。
2.閉眼供養の対象
閉眼供養の対象となるのは、主に以下のようなものが挙げられます。
- 改葬(墓じまい)をするお墓
- 処分する仏壇・仏像・位牌
- 遺影
- 遺品
- 人形
人形や遺品の場合は、宗教者によって魂を入れたものではないので、必ずしも閉眼供養をしなければならないものではありませんが、大切にしていた持ち主の心が宿っていると信じられているものに対して、閉眼供養を希望する人は少なくありません。
3.閉眼供養の手配
閉眼供養は、菩提寺があるならば菩提寺に依頼します。
特に、境内墓地にあるお墓の改葬(墓じまい)を行うのであれば、必ず菩提寺に依頼しましょう。
公営霊園や共同墓地などを利用しており、菩提寺がない場合には、改葬(墓じまい)を依頼している業者に閉眼供養を行う僧侶の手配について相談すると良いでしょう。
神道の場合は、付き合いのある神社が無ければ、改葬(墓じまい)の業者に神社の紹介を依頼しましょう。
仏壇・仏具の閉眼供養の場合は、新しい仏壇を購入した仏具店に、閉眼供養を行う僧侶の手配を依頼することもできます。
4.閉眼供養の流れ
閉眼供養の流れは以下の通りです。
- 1. 日程を決める
僧侶等の宗教者と相談し、日時を決定。
改葬(墓じまい)のための閉眼供養の場合は、工事の前に行われる。 - 2. 必要な準備をする
- お布施を準備。
- 供物(仏教の場合、果物・お菓子・お花・線香など)を用意。
- 自宅で行う場合は、仏壇や仏具を清掃する。
- 3. 儀式の催行(魂抜き) 宗教者の読経や祭詞の奏上を行い、仏壇や仏像、お位牌などに宿るとされる「魂」を抜く儀式を執り行う
- 4.閉眼供養後の対応
- お墓の場合は、納められている遺骨を取り出し、撤去・原状回復工事を行う。
- 仏壇の場合は、仏壇処理業者に依頼するか、自治体の定めに従い廃棄する。
5.閉眼供養にかかる費用
閉眼供養にかかる費用は、以下の通りです。
- 宗教家へのお礼:お寺へのお布施としては、3万円~5万円と言われていますが、お寺様により異なりますので、菩提寺がある場合は菩提寺のご意向に従いましょう。 神道の場合は、祈祷料がかかります。祈祷料は神社により異なります。
- お車代:交通費として5千円~1万円程度が目安ですが、遠方の菩提寺から僧侶にお越しいただく場合は、相談の上適切な金額をご用意することをおすすめします。
- 御膳料:閉眼供養では、一般的には食事を提供することはありませんが、御膳料をお渡しすることが通例です。
閉眼供養は故人やご先祖様への敬意を表す大切な儀式なので、適切な方法で行うことが重要です。
これまでお世話になったお墓や仏壇、また境内墓地からの墓じまいであればお世話になったお寺に対して感謝の気持ちを大切にしたいものです。