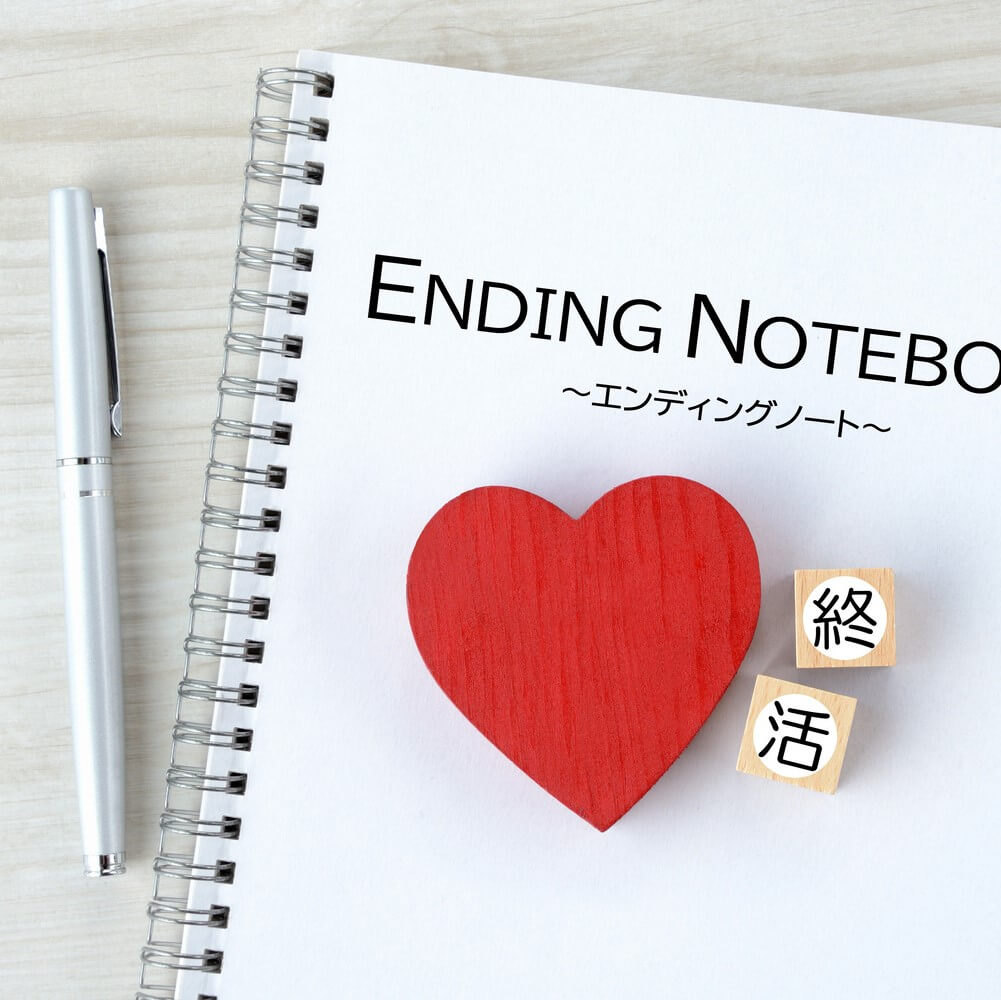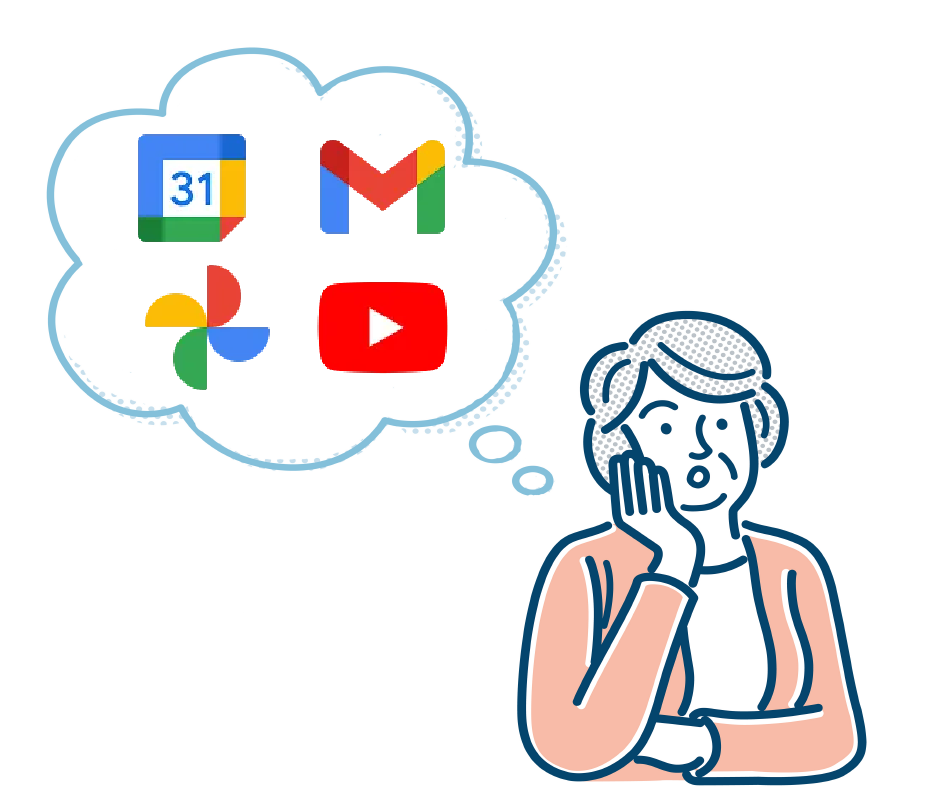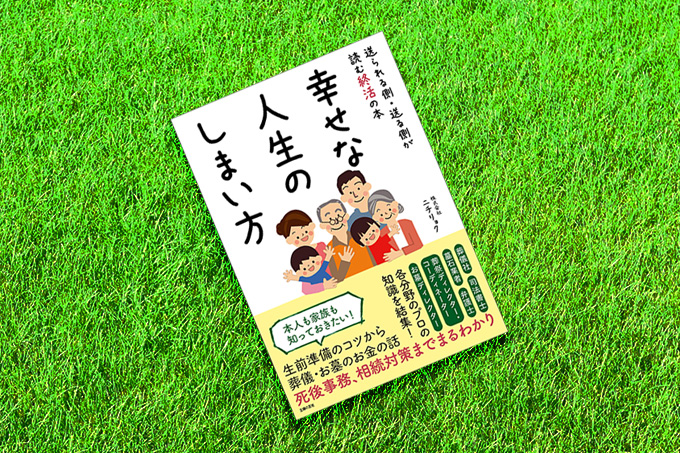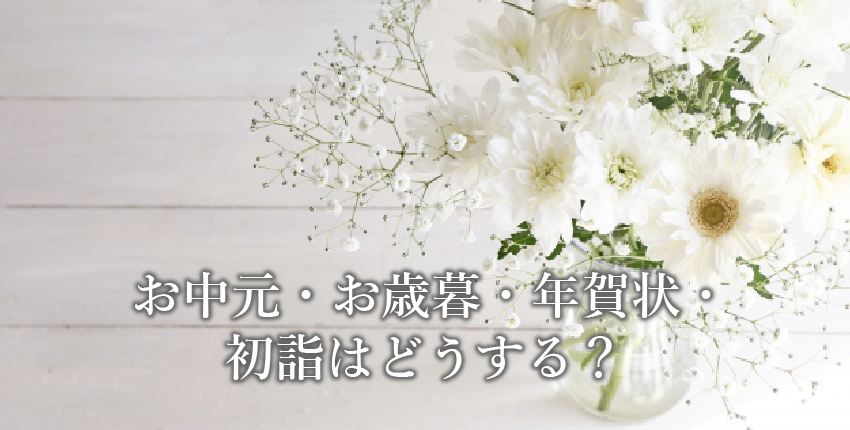
特に、喪中や忌中といった言葉を耳にしながらも、「具体的にどう過ごすべきか」「何をしてはいけないのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
ここでは、喪中・忌中の基本的なマナーについて、ご紹介します。
大切なのは、形にとらわれすぎることなく、故人様を偲び、ご自身の心を労わることですが、古くからの習わしを知ることも、心を整理する一助となるでしょう。
1. 喪中・忌中の違いとは?
まず、「忌中(きちゅう)」と「喪中(もちゅう)」は、しばしば混同されますが、厳密には異なる期間と意味を持ちます。
- 忌中(きちゅう)
- 故人様が亡くなられてから、四十九日(または三十五日)の法要を終えるまでの期間を指すのが一般的です。この期間は、故人様の魂がまだこの世に留まっていると考えられたり、死の穢れ(けがれ)が及ぶ期間とされたりします(主に神道の考え方)。遺族は、故人様の冥福を祈り、身を慎んで静かに過ごします。
この期間は、特に慶事(お祝い事)への参加や、神社への参拝は避けるべきとされています。また、派手なことや、公の場に出ることも慎むのが習わしです。 - 喪中(もちゅう):
- 忌明け(四十九日法要後)から、一年間(故人様の一周忌まで)を指すのが一般的です。この期間は、故人様への哀悼の意を表し、慶事への参加や、自分が主催するお祝い事を控える期間です。忌中のような厳しい制約はありませんが、お正月のお祝いなどは控えるのが一般的です。
喪中は、故人様を亡くした悲しみから徐々に立ち直り、日常生活に戻っていくための準備期間ともいえます。
忌中はより身を慎む短い期間、喪中は故人様を偲び、お祝い事を控える比較的長い期間、と理解していただくと良いでしょう。
喪中・忌中の期間はどれくらい?
喪中・忌中の期間は、故人様との関係性によって異なります。伝統的な考え方では、以下のようになります。
- 忌中:
- 父母、配偶者、子:50日(仏式では四十九日法要までとする考え方が一般的です)
祖父母、兄弟姉妹、孫:30日
上記以外:比較的短い期間、または設けない場合もあります。 - 喪中:
- 父母、配偶者:1年
子:1年
祖父母:半年〜1年
兄弟姉妹:半年
上記以外:設けない場合もあります。
これらの期間はあくまで目安であり、地域や各家庭の考え方によって違いがあります。近年では、故人様との関係性の深さや、ご自身の気持ちに合わせて、これらの期間を柔軟に考えることも増えています。大切なのは、期間に縛られすぎることではなく、故人様を偲び、ご自身の心を癒す時間を持つことです。
2.喪中・忌中で心掛けるべきこととは?
喪中・忌中に共通して心掛けるべきこと、そしてそれぞれの期間で特に注意したい点があります。
共通して心掛けること
- 慶事への参加・主催を控える: 結婚式、出産祝い、新築祝いなど、お祝い事への参加や、自身が主催するお祝い事は避けるのが一般的です。やむを得ず参加する場合や、どうしても開催する必要がある場合は、先方に事情を説明し、理解を得るように努めましょう。
- 派手な言動や行動を慎む: 騒がしいパーティーや宴会への参加、新しいものを購入する、旅行に出かけるといった行動は、控えるのが望ましいとされてきました。故人様への哀悼の意を示す期間として、静かに過ごすことを心掛けます。
- 故人様を偲び、心を整理する時間を持つ: この期間は、悲しみを乗り越え、故人様との思い出を振り返り、心の内を整理するための大切な時間です。無理に明るく振る舞う必要はありません。ご自身の感情に寄り添い、ゆっくりと過ごしましょう。
特に忌中(四十九日まで)に心掛けること
- 神棚の封印(神棚封じ): 神道では死を穢れと捉えるため、忌中は家の神棚に白い半紙などを貼って封じ、神棚へのお供えや拝礼を一時的に控えます。
- 神社への参拝を控える: 同様に、神道の考え方から、忌中は神社への参拝は避けるのが一般的です。お宮参りや七五三などの参拝も延期します。お寺への参拝は宗派によって考えが異なりますが、一般的には問題ないとされます。
- 故人様への供養に専念する: ご自宅での読経、お墓参り、位牌や遺影への語りかけなど、故人様への供養に時間を使います。
近年では、これらの慣習もライフスタイルの変化に合わせて柔軟になっています。
例えば、忌中であっても、仕事や日常生活に支障が出ない範囲で外出したり、最低限の付き合いを続けたりすることは一般的になってきました。大切なのは、形式だけでなく、故人様への想いを忘れず、ご自身の心に正直に行動することです。
3.お中元・お歳暮・年賀状・初詣をどうすべきか
季節の挨拶や行事は、喪中・忌中期間と重なることが多く、特にどのように対応すべきか迷われる点です。それぞれについてご説明します。
お中元・お歳暮について
お中元やお歳暮は、日頃お世話になっている方への感謝の気持ちを伝えるための贈り物であり、基本的にお祝い事ではありません。
したがって、自身が喪中の場合でも、例年通り贈ることは問題ありません。
ただし、いくつか注意点があります。
- 贈る時期: 通常通りの時期(お中元は夏、お歳暮は年末)で問題ありません。
- のし(熨斗)の選び方: 慶事用の紅白ののしは避け、弔事用の黒白または双銀の結び切りののし、あるいは略式として無地の奉書紙や白い短冊を使用するのが一般的です。表書きは「御中元」「御歳暮」とします。
- 添え状: 添え状を添える場合は、時候の挨拶は控えめにし、喪中のため簡単なご挨拶とさせていただく旨を書き添えると丁寧です。
- 相手が喪中の場合: 相手が喪中の場合でも、お中元・お歳暮を贈ることは問題ありません。相手の方も、例年通りであれば受け取るのが一般的です。ただし、先方の心情を察し、贈る時期や品物を考慮すると良いでしょう。
年賀状について
年賀状は、新年を祝うためのご挨拶状ですので、自身が喪中の場合は、年賀状を送ることは控えます。
代わりに、年末までに「喪中欠礼のはがき(喪中ハガキ)」を送り、翌年の年賀状でのご挨拶を遠慮する旨をお知らせします。
- 喪中ハガキを出す時期: 相手が年賀状の準備を始める前に届くように、11月中旬から12月上旬までに投函するのが一般的です。遅くとも12月15日までには届くようにしましょう。
- 喪中ハガキの内容:誰が、いつ亡くなったか(続柄と月日)を記します。
喪中につき、新年の挨拶を欠礼する旨を伝えます。
日頃の感謝や、今後も変わらぬお付き合いをお願いする言葉などを添えます。
差出人の名前と住所を記載します。
句読点は使用しないのが慣例です。 - 相手から年賀状が届いた場合: 喪中ハガキを出したにも関わらず年賀状が届いた場合、それは先方が喪中ハガキを見落としたか、年末に急な不幸があったなど、特別な事情がある場合が考えられます。
このような場合は、松の内(通常1月7日まで)が明けてから「寒中見舞い(かんちゅうみまい)」として返信するのがマナーです。 - 寒中見舞いを出す時期: 松の内が明けた1月8日から、立春(2月4日頃)までに出します。
- 寒中見舞いの内容: いただいた年賀状へのお礼、故人が亡くなったため喪中であること、先方の無事を祈る言葉などを記します。
- 相手が喪中の場合: 相手から喪中ハガキが届いたら、翌年の年賀状を送ることは控えます。年明けに寒中見舞いとして、相手を気遣うメッセージを送ると丁寧です。
初詣について
初詣は、一年の始まりに神社やお寺に参拝し、神仏に無事や幸福を祈る行事です。
- 忌中(四十九日まで)の場合:
神道の考え方では、死の穢れがある期間として神社への参拝は避けるのが一般的です。
お寺への参拝は、宗派によっては問題ないとする考え方もありますが、故人様を亡くして間もない時期であり、賑やかな場所に出かけることを控える意味でも、初詣は見送るのが望ましいでしょう。 - 喪中(一周忌まで)の場合:
喪中期間中の初詣については、考え方が分かれます。
伝統的には避けるべきとされてきましたが、近年では、静かに故人様を偲びつつお寺へ参拝する方や、神社の賑やかな雰囲気を避け、静かな時期に参拝する方など、柔軟に対応する方も増えています。 もし、どうしても参拝したいという気持ちが強い場合は、人出の少ない時期を選んだり、故人様の冥福を祈る場としてお寺を選んだりするなど、ご自身の心情と向き合って判断することが大切です。
あるいは、故人様を自宅や墓前で静かに偲び、新しい年の始まりに思いを馳せることも、一つの過ごし方です。
まとめ
忌中・喪中のマナーは、故人様への敬意と、遺族の悲しみに寄り添うための古くからの知恵です。しかし、最も大切なことは、形式にとらわれすぎず、ご自身の心と向き合い、故人様を大切に想う気持ちです。
今回ご紹介した内容は一般的な目安であり、地域やご家庭の慣習、宗教・宗派によって異なる場合もあります。
迷われた際は、株式会社ニチリョクお客様相談室(フリーダイヤル0120-300-100)へお気軽にお問合せください。