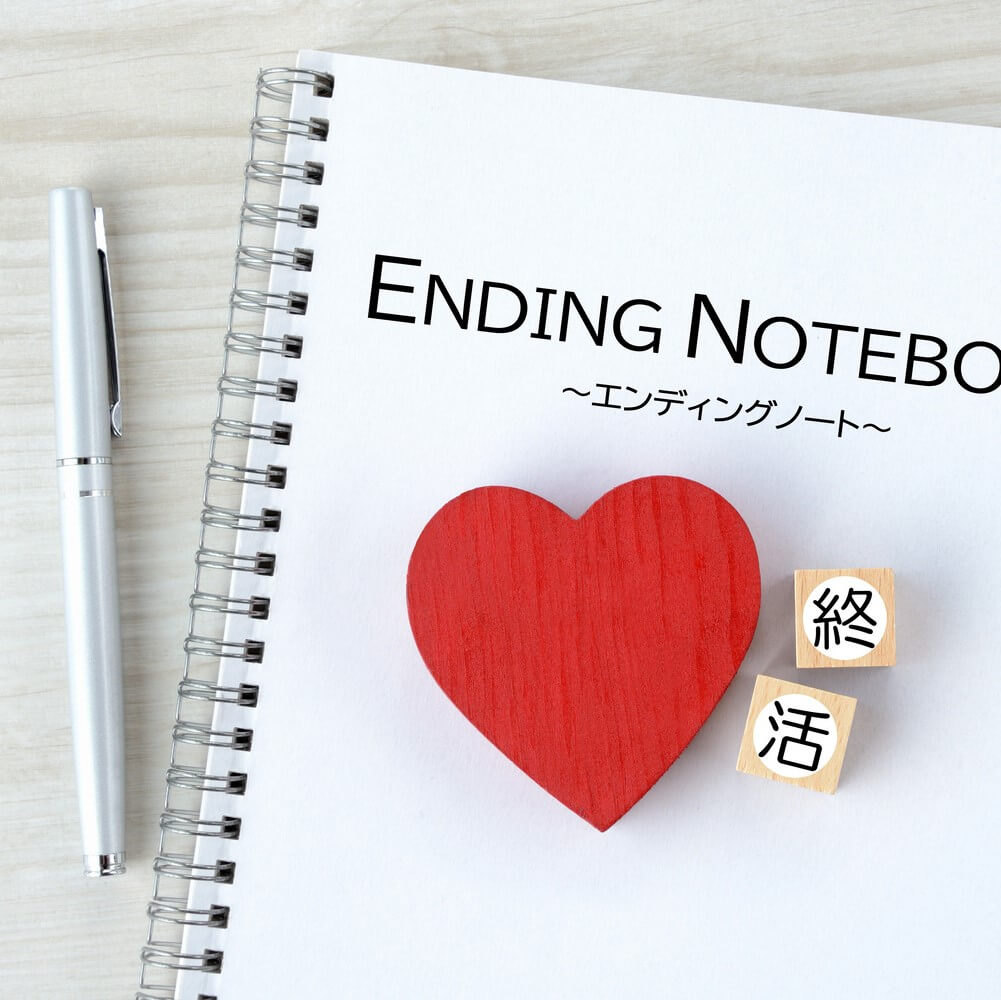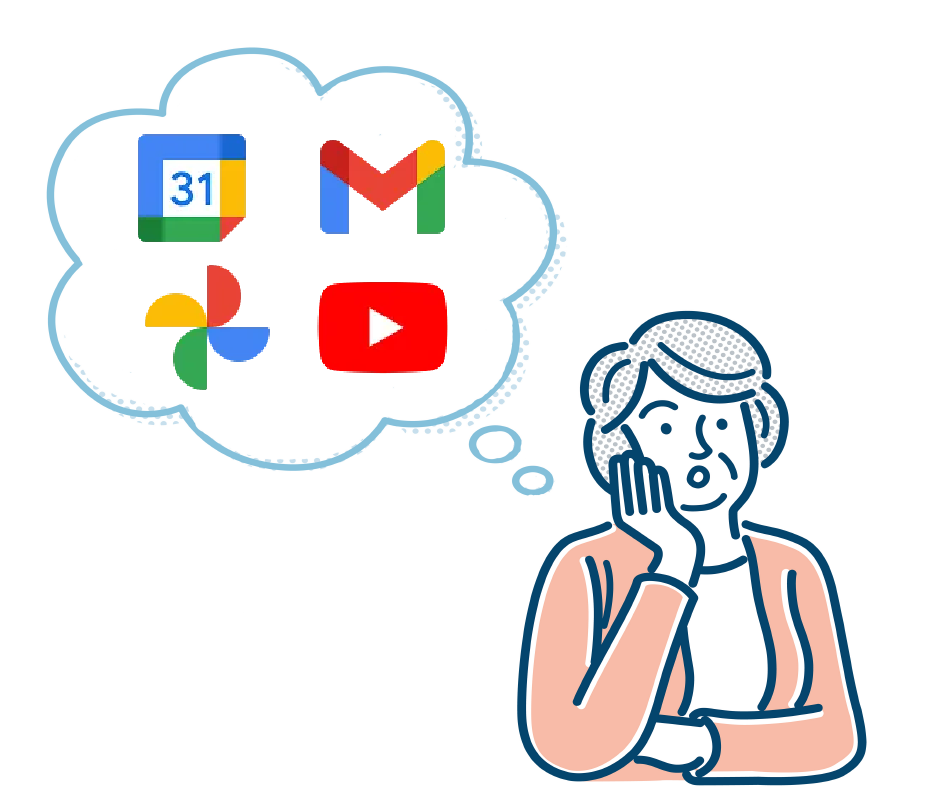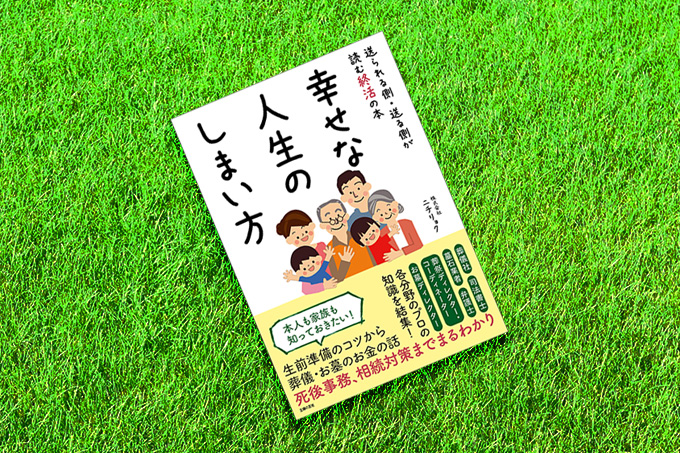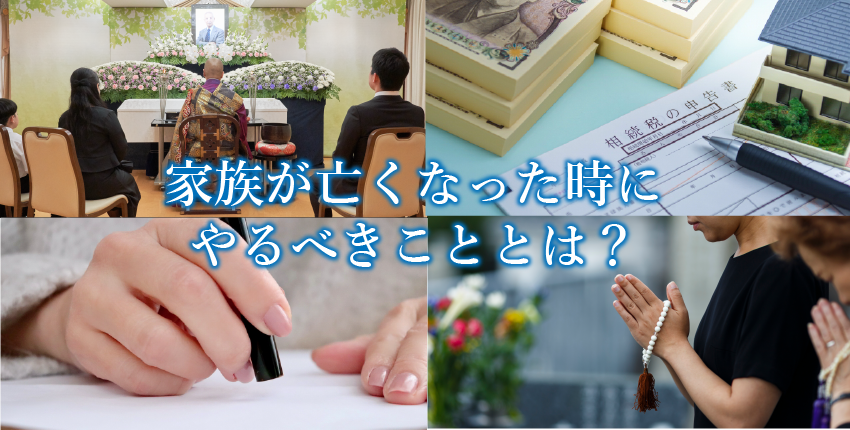
親や家族の死は、感情的な悲しみに加えて、多くの「やらなければならないこと」に追われる現実があります。
特に葬儀やその後の手続きには期限があるものも多く、事前に知っておくことで、心の余裕が生まれます。
この記事では、親や家族が亡くなった直後から数カ月後までにやるべきことを時系列で整理し、それぞれに必要な対応をわかりやすく解説します。
1. 死亡直後に行うこと(当日〜翌日)
- 医師による死亡確認と「死亡診断書」の受け取り
病院で亡くなった場合は、医師が死亡を確認し、「死亡診断書(死体検案書)」を作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医や救急搬送先の医師に依頼します。
これはすべての手続きの出発点になる重要書類です。
念のため、死亡診断書を数部コピーしておくと、後の手続きの際に安心です。 - 葬儀社への連絡
病院で亡くなると、多くの場合、すぐに遺体搬送が必要になります。
病院の霊安室には長時間滞在することはできず、早めの搬送を催促する病院も中にはあります。
時間の猶予がない中でスマホで検索して出てきた葬儀社に搬送依頼をしたことで、その後の葬儀に後悔した方もいらっしゃいます。
そのような事態を避けるためには、事前に複数の葬儀社に相談をして、信頼できる葬儀社を選定しておくことが大切です。
株式会社ニチリョクは、葬儀の事前相談を随時承っています(申し込み:フリーダイヤル0120-300-100)。
2. 役所での手続き(死亡後7日以内)
- 死亡届の提出と火葬許可証の取得
死亡診断書と一体になっている「死亡届」を、亡くなった方の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。
提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」です。
これと引き換えに「火葬許可証」が発行されます。
3. 葬儀の準備と実施(死亡から1~3日後)
- 葬儀の形式と規模を決定
宗教者の有無、会葬者の人数、予算などを踏まえ、葬儀社と打ち合わせを行います。
コロナ禍においては、直葬や家族葬を選ぶ方が多かったのですが、コロナ禍以降は多くの方が参列する葬儀も増えています。
故人様の人間関係を確認したうえで、決めることをおすすめします。 - 関係者への連絡
親族や関係の深い友人、故人の職場関係者などへ連絡します。最近はLINEやメールで連絡する人も増えていますが、高齢の親族には電話で連絡する方が親切でしょう。
4.火葬・埋葬の手続き
- 火葬の実施
「火葬許可証」は火葬時に提出します。
火葬後には「埋葬許可証」が遺族に渡されます。
これはお墓への納骨時に必要なので、必ず保管してください。 - 納骨・お墓の準備
すでにお墓がある場合は、寺院や霊園と納骨日を調整します。
新たにお墓を探す場合、宗教・宗旨宗派の希望や、場所、他の家族も一緒に入るかどうかなど、条件を明確にしましょう。
お墓には、公営霊園・民営霊園・境内墓地があり、お墓の種類も多岐に渡るようになっています。
インターネットを活用したり、お墓の専門家に相談できるニチリョクの「お墓の相談サロン」を利用すると、スムーズにお墓選びができます。
納骨は四十九日や一周忌など、法要で人が集まりやすい時に行う方が多いですが、期限があるわけではないのでご安心ください。
5.死亡後の主な名義変更・解約手続き(1週間〜1カ月)
- 公的手続き(年金・健康保険・介護保険)
- 【年金】年金受給者が亡くなった場合、「年金受給者死亡届(報告書)」を提出。未支給年金は相続人が受け取れます。
- 【健康保険】保険証の返還、葬祭費(または埋葬料)の申請も忘れずに。
- 金融機関の手続き
銀行口座は死亡の事実が伝わると凍結されます。
相続手続きが完了するまでは引き出せなくなります。
預貯金、証券、クレジットカード、借入金など、故人名義の金融資産はリストアップし、順次手続きを行います。 - ライフライン・契約の解約
電気・ガス・水道・電話・インターネット・新聞・クレジットカード・動画配信サービスのサブスクリプションなど、日常生活にかかわる契約は、利用停止と名義変更または解約が必要です。書類に「死亡診断書のコピー」が必要なケースもあります。
6.相続・遺産に関する手続き(1カ月〜4カ月)
- 遺言書の確認
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
ただし、自筆証書遺言でも、法務局で保管されているものは検認は不要です。
公正証書遺言なら検認は不要ですが、いずれも内容を精査して相続手続きに移ります。 - 相続人の確定と遺産分割協議
故人の戸籍を調べ、法定相続人を確定させます。
その上で相続人全員で「遺産分割協議書」を作成します。
これにより、不動産や預貯金の口座などの名義変更が可能になります。
7. 四十九日法要とその後の弔い(1カ月半〜)
- 四十九日法要の準備
菩提寺がある場合は菩提寺に相談し、法要の日程を決めます。お墓がすでにある場合、納骨をこの日に合わせるケースが多いです。
会食や引き出物を用意するかどうかも家族で話し合いましょう。 - 位牌・仏壇・遺影の準備
初七日~四十九日までの間に、白木位牌から本位牌へと切り替えるのが一般的です。
仏壇がない場合は、四十九日までに位牌とともに手配をしましょう。
近年は、住宅事情に合わせた大小さまざまなサイズの仏壇がありますので、仏壇店に相談して、住まいにあった仏壇を用意しましょう。
8.まとめ:事前の備えが心の余裕につながります
人の死は、日常生活の延長線上にある一方で、多くの実務的手続きを伴います。
これらは「悲しむ間もない」と言われるほど忙しくなることが多いため、今のうちから情報を把握しておくことで、その時を迎えたときに落ち着いて対応できるようになります。
「うちの親はまだ元気だから」「親に死んだときの話なんて切り出せない」と思いがちですが、事前の話し合いや準備が、いざという時に残される家族にとって大きな支えとなります。この記事がその一歩となれば幸いです。