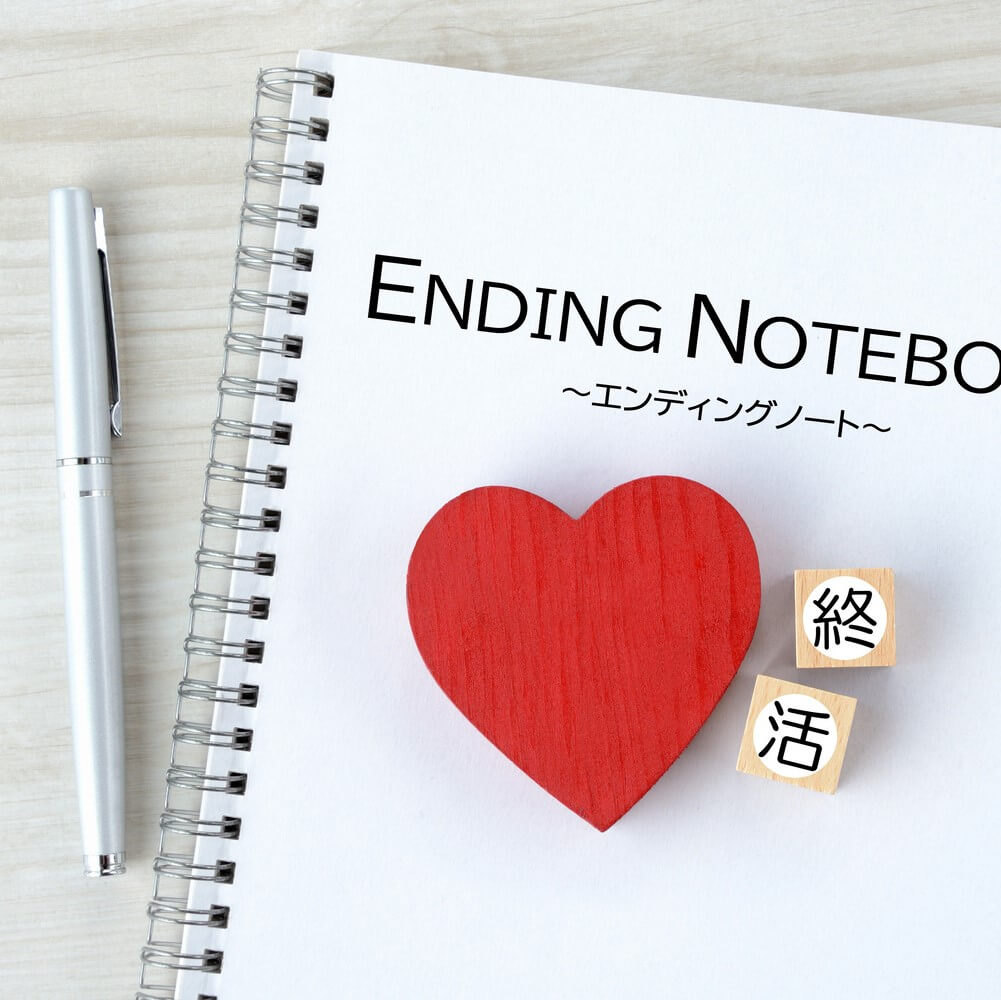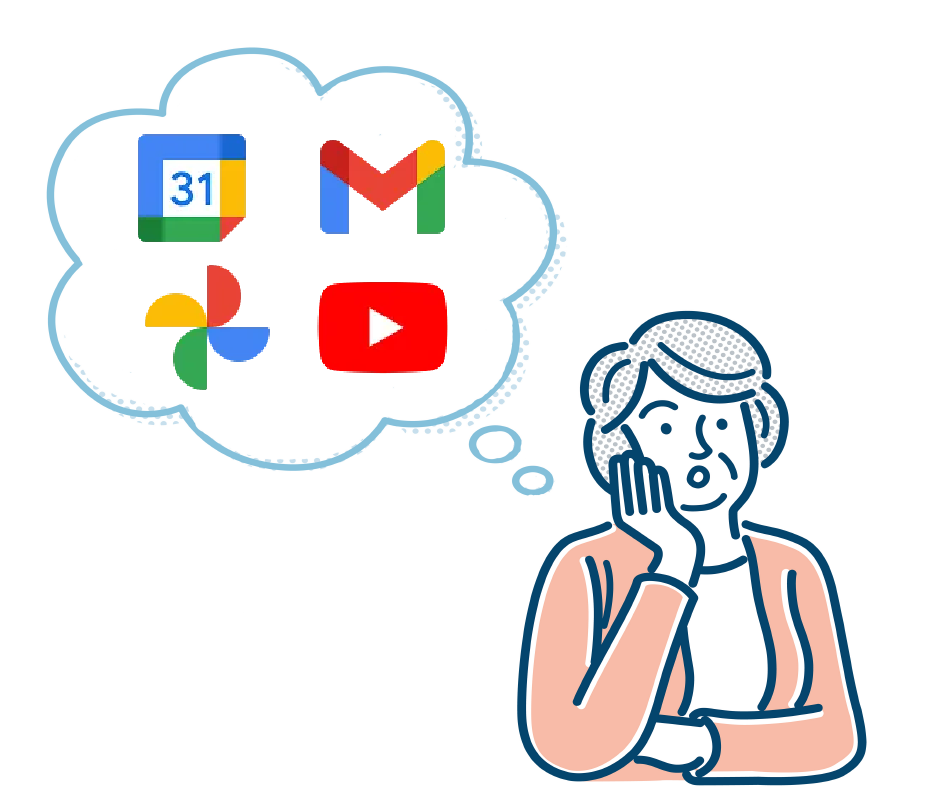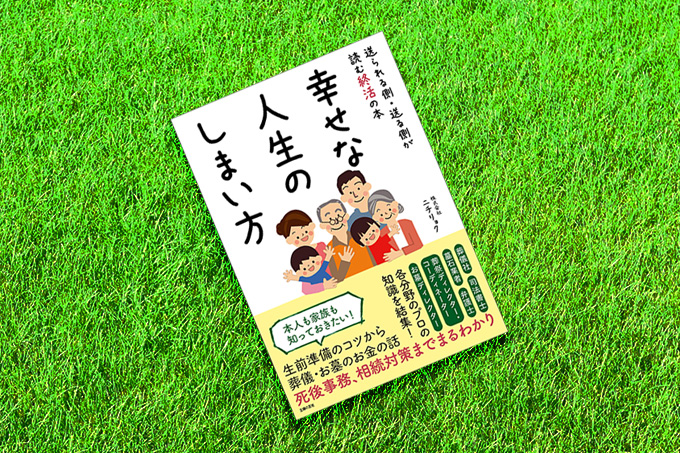かつてのお墓といえば、人里離れた場所だったり、郊外に作られていたりしており、往復にも時間がかかり、現地に着いたら草むしりに墓掃除でお墓参りは一日がかりという方も少なくありませんでした。
しかし、高齢化が進む今、遠方のお墓へのお参りは体力的に厳しくなり、今あるお墓を閉じて、家の近くにお墓を移そうとする人が年々増えており、そのような人がお墓を探す条件として挙げているのが「家の近くにあること」です。
お墓を家の近くに持ってきて、かつお墓参りの負担を軽減したいと考えるのであれば、ぜひ候補に入れて欲しいのが、納骨堂です。
この記事では、納骨堂とは何か、納骨堂の種類、納骨堂のメリット・デメリット・家の近くの納骨堂を探す際のチェックポイントや実際に探している人から良く聞かれる質問とその答えをご紹介します。
納骨堂とは
納骨堂とは、遺骨を収蔵するための施設で、主に都市部などで墓地の代わりに利用されています。
従来のお墓とは異なり、室内や建物内に設けられた納骨室に遺骨を安置します。
かつては、遺骨の一時預かり場所として機能していましたが、近年遺骨を長期間にわたり収蔵し、お墓と同様に使われるようになっています。
納骨堂は、寺院をはじめとする宗教施設に設けられているほか、近年は自治体の運営する公営墓地の中にも設けられるようになっています。
納骨堂の種類
納骨堂にはいろいろなタイプがあります。
ここでは、納骨堂の種類についてご説明します。
- 自動搬送式
- 利用者の情報が納められているICカードを読み取ると、自動的に参拝口にご遺骨の入った厨子が運ばれ、遺骨に手を合わせてお参りができます。
赤坂一ツ木陵苑のように、墓石を模した参拝口が設けられているところは、従来のお墓の印象が強い人にも受け入れられています。
- ロッカー式
- 個別に区切られた納骨棚の中に遺骨を収蔵します。
ロッカーのサイズにより、納骨可能なご遺骨の数は変わります。 - 棚式
- 棚に複数の遺骨を並べて安置します。
一体あたりの価格設定のところが多く、複数収蔵したい場合は、遺骨の数だけ費用がかかる可能性があります。 - 仏壇式
- 仏壇の下に設けられた納骨室の中に遺骨を安置します。
比較的大型の納骨室を備えていることから、複数のご遺骨を納めたい方に選ばれています。
他人の遺骨と一緒に収蔵されたくないと考える人に向いています。 - 合葬式
- 遺骨を他の方と一緒に合同で供養します。
遺骨を骨壺から取り出して合祀することが多く、費用は低めに抑えられている一方で、いったん収蔵したら遺骨を取り出せないこともあります。
納骨堂のメリット・デメリット
納骨堂は、屋内の施設ということもあり、他のお墓とは異なる部分が多くあります。
これらを理解したうえで、検討することが大切です。ここでは、納骨堂のメリット・デメリットをご紹介します。
メリット
- アクセスの良さ: 霊園に比べ、都市部にあることが多く、公共交通機関が利用できる交通の便の良いところにあるところが多いです。
- 天候に左右されない: 屋内にある施設なので、気温や天候を気にせず参拝が可能です。
- 管理が簡単: 管理を運営側に任せられる場合が多く、利用者が掃除をする必要はありません。
- 費用が比較的安い: 同程度遺骨を納められる一般的なお墓に比べ、納骨堂は費用が安価な傾向があります。
デメリット
- 空間の制限: 遺骨の収蔵スペースが限られている施設もあります。その場合、多くの遺骨を納める場合には粉骨する必要があります。
- お参りの仕方が異なる:花立がなかったり、お供え物を置ける場所がないなど、墓のようなお参りができないことから、 先祖代々の墓を重要視する人にとっては抵抗を感じる人もいます。
赤坂一ツ木陵苑や大須陵苑のような自動搬送式納骨堂は、比較的参拝口が大きかったり、お供えものを置くスペースは設けられています。 - 納骨期間が定められている場合が多い: 管理費が不要な納骨堂の場合、納骨期間が設定されているところが多く、その期間が過ぎると合祀されます。
- 参拝時間が限られている:納骨堂は開館時間内のみお参りが可能なところが殆どです。屋外の墓地のようにいつでもお参りができるわけではないので、お参りに不便のない時間帯かあらかじめ確認しましょう。
家の近くの納骨堂を探すときのチェックポイント
家の近くの納骨堂を探すうえで、チェックしておきたい項目をまとめました。納骨堂を選定するときに参考にしてください。
- 立地とアクセス
- 自宅や親族の住居から通いやすい場所か
- 公共交通機関の利便性や駐車場の有無
- 費用とプラン
- 初期費用、管理費・護持会費、納骨期間など、自分達の希望に合っているかどうか
- 宗教面
- 自分の家族の宗教や宗派を受け入れるかどうか
- 施設・設備
- 参拝スペース、休憩所、エレベーターなどの設備があるかどうか
- 管理体制
- 管理事務所・寺務所の体制(スタッフの人数、セキュリティや清掃の状況、管理事務所・寺務所で法要の手配がどの範囲まで可能か等)
- 契約内容
- 自分の利用する区画の条件や納骨期間、納骨期間後のご遺骨の対応等。
家の近くの納骨堂を探している人が良く聞く質問と答え
Q1: 納骨堂とお墓の違いは何ですか?
A1: 納骨堂は屋内に遺骨を収蔵する施設で、天候に左右されず管理が簡単です。一方、お墓は屋外に建てられ、伝統的な墓石の形式が一般的です。
Q2: 永代供養は本当に永遠ですか?
A2: 永代供養は、経営主体である寺院が責任をもってお墓とそこに眠る故人様を守るという意味であり、永遠に守るという意味ではありません。
Q3: 納骨堂は誰でも利用できますか?
A3: 納骨堂の経営主体の方針によります。自治体の運営する公営の納骨堂であれば、宗旨宗派を問わず利用することができます。寺院の運営する納骨堂の場合は、それぞれの寺院の方針がありますので、事前に確認する必要があります。また、宗旨宗派を問わず利用できる寺院運営の納骨堂であっても、館内の法事には制約がある可能性がありますので、合わせて確認しましょう。
Q4: 費用はどのくらいかかりますか?
A4: 立地や形式によりますが、初期費用は10万–150万円程度が一般的で、維持費は年間数千円–10万円程度です。納骨堂の形式によっては、管理費が不要なものもあります。
Q5: 遺骨はずっと保管されますか?
A5: 多くの場合、一定期間後に骨壺から遺骨を取り出して合祀墓に移す(合祀)規定があります。管理費・護持会費を納入している限りは使用可能な納骨堂の場合は、管理費・護持会費が一定期間納入されなくなると合祀されるところが大半です。納骨堂により規定が異なりますので、事前に確認することが大切です。
Q6: 納骨堂を利用する場合、住まいの所在地は限定されますか?
A6: 公営の納骨堂の場合、住所が運営する市町村内にあることを条件にするところが殆どです。寺院が運営する納骨堂の場合は、住居の所在地は問われません。
Q7: ペットの遺骨も納骨できますか?
A7: 経営主体の方針によります。一部の納骨堂ではペット専用やペットと一緒に納骨できる施設があります。
Q8: 参拝時間に制限はありますか?
A8: 多くの施設では参拝時間が定められています。
納骨堂は現代のニーズに合った新しい供養の形です。
家族の希望やライフスタイルに合わせて適切な施設を選ぶことで、安心して大切な方を供養することができます。
この記事では、家の近くで納骨堂を探すうえで知っておくべきことをご紹介いたしました。後悔の無いお墓探しのためにぜひ役立ててください。