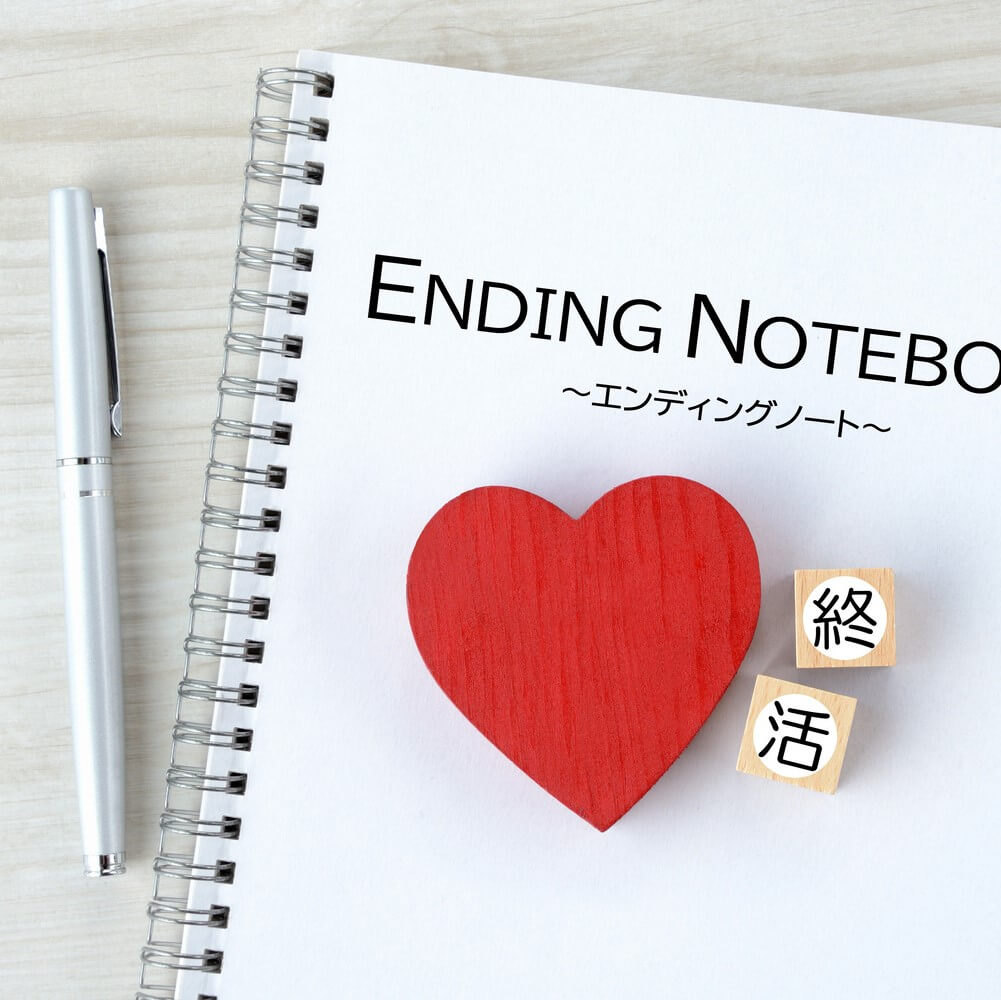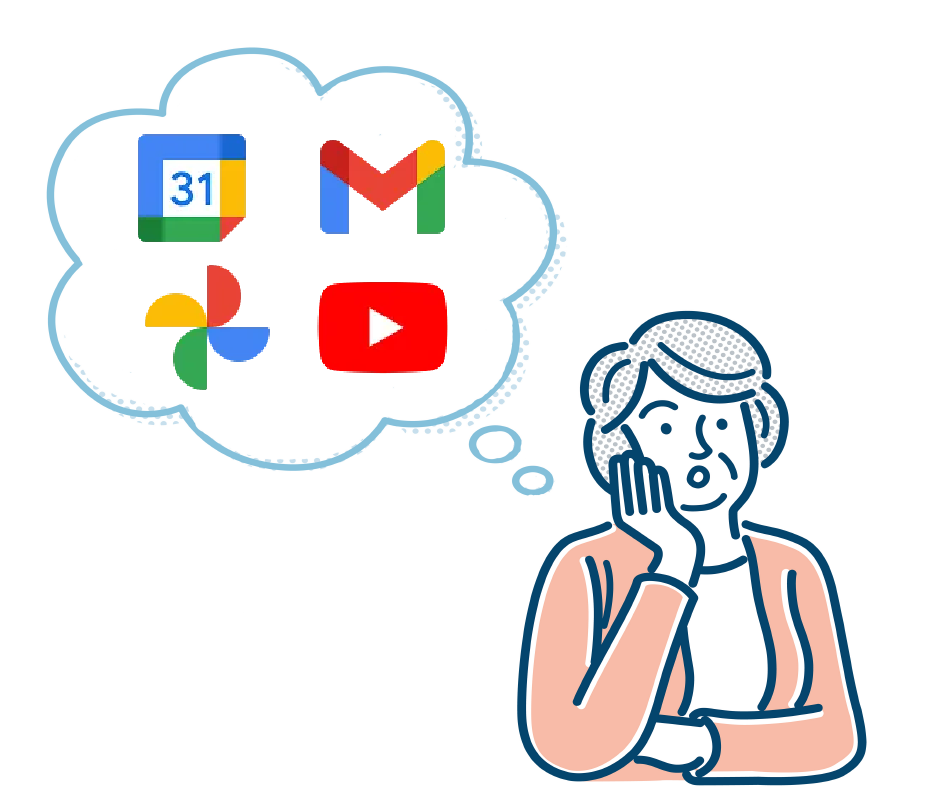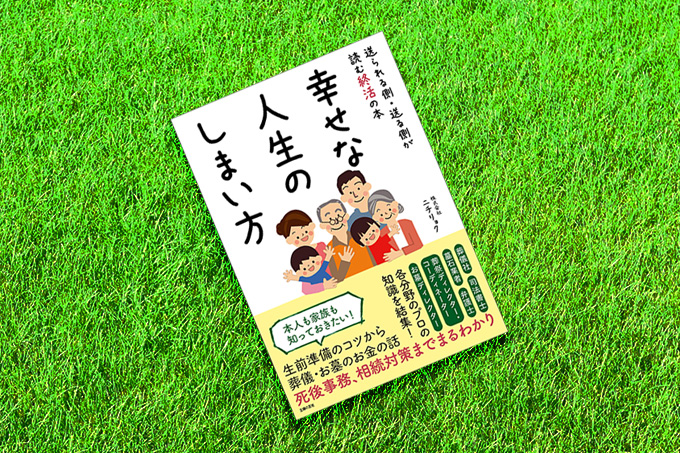エンディングノートを準備するとき、やってはいけない3つのこと
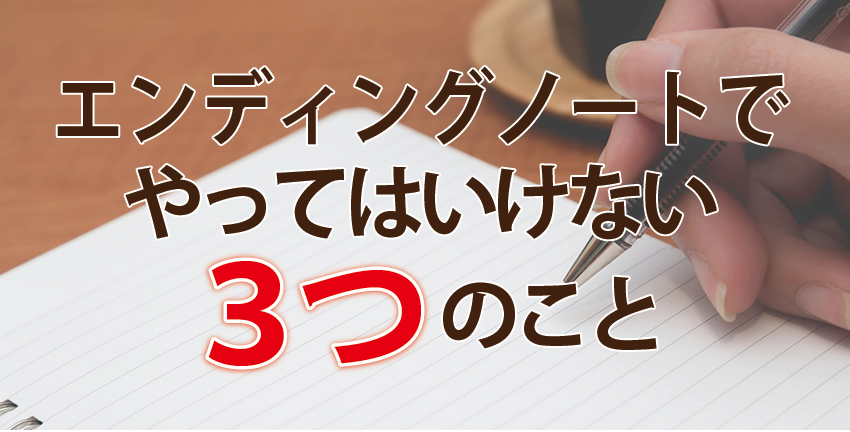
NGその1 遺言はエンディングノートに書いてはいけません!

エンディングノートには、葬儀やお墓をはじめ、終活に関することや自分自身の気持ちなどを記入し家族に伝えるためのツールですが、実は書いても意味がないことがあります。それは主に以下の3点です。
- (1)相続に関すること
- (2)財産の処分に関すること
- (3) 身分に関すること
具体的には
(1)は、「法定相続分と異なる割合での相続分の指定」や「相続人の廃除や、廃除の取消し」等、(2)は「財産の遺贈」をはじめとする財産の処分等、(3)は「婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子どもの認知」等です。
これらに関する意思表示は、法律に定められた方式で作られた遺言で行わなければならず、これに従わなければ全て無効なのです。
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。どちらを選ぶにしても、残される家族が納得し、トラブルなく相続を行えるような内容にし、恙なく執行できるように準備しておきたいものです。自筆証書遺言は自分で書けますが、法的な要件を確実に満たすものでなければ、これもまた折角用意しても意味がないので、専門家にアドバイスを受けながら作成する、もしくは公正証書遺言を選択するのが安心でしょう。
エンディングノートには、遺言を用意していることとその種類(自筆証書遺言か公正証書遺言か)、自筆遺言であれば置いてある場所を記載しておくと、残された家族は遺言なしで相続協議をせずに済むので安心ですね。
NGその2 古い情報を残すのは混乱のもと!
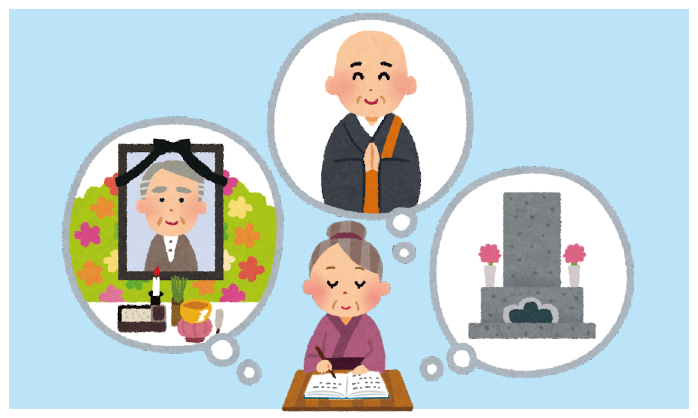
生きているうちに、考えが変わっていくことはよくあること。だからエンディングノートは一度書いたからと言ってそれで終わりではなく、定期的に見直して、その時の想いに合わせて書き直すとと良いでしょう。
その際に気をつけたいのが、古い記述と新しい記述が区別がつくようにすることです。古い記述はそれとわかるよう棒線で消したり、ページごと差し替え、家族が読むときに混乱が無いようにしておいた方が良いでしょう。特に、何度も書き換え、書きこむスペースがなくなってきた場合には、該当ページを差し替えると良いでしょう。
このウェブサイトの右上のボタンから入手できるPDFのものであれば、最初に全てのページを印刷してファイルに閉じ、必要に応じて書き換えたページのみ差し替えができるので、何度も内容を見直し、書き換えをする場合には便利です。
NGその3 全てが終わってから見つかるのでは遅すぎる!
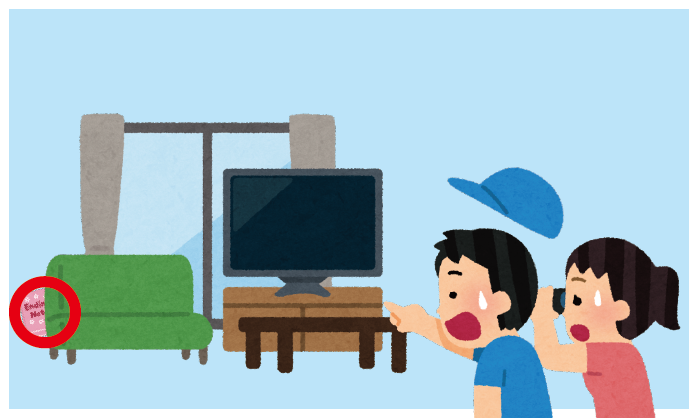
エンディングノートは、書く本人と、それを読む家族のためのものです。それがいざというときに家族がエンディングノートの存在を知らず、葬儀を終えて家の片づけをしているときに、荷物の中からエンディングノートが見つかった、となっては、書いた意味がなくなってしまいますし、故人の意思を尊重できなかったと遺族に後悔をさせてしまうことにもなります。
エンディングノートを用意したら、書き終わってなくても家族にその存在を知らせておきましょう。
- また、タンスの中にしまいこんだりせず、目につきやすいところに置くようにし、いざというときにすぐに見つかるようにしておきましょう。
書いた本人が亡くなるまで、家族にエンディングノートを見せてはいけないことなどありません。むしろ、エンディングノートを書いていることを家族に伝え、エンディングノートを見ながら家族とざっくばらんに話してみてはいかがでしょうか。