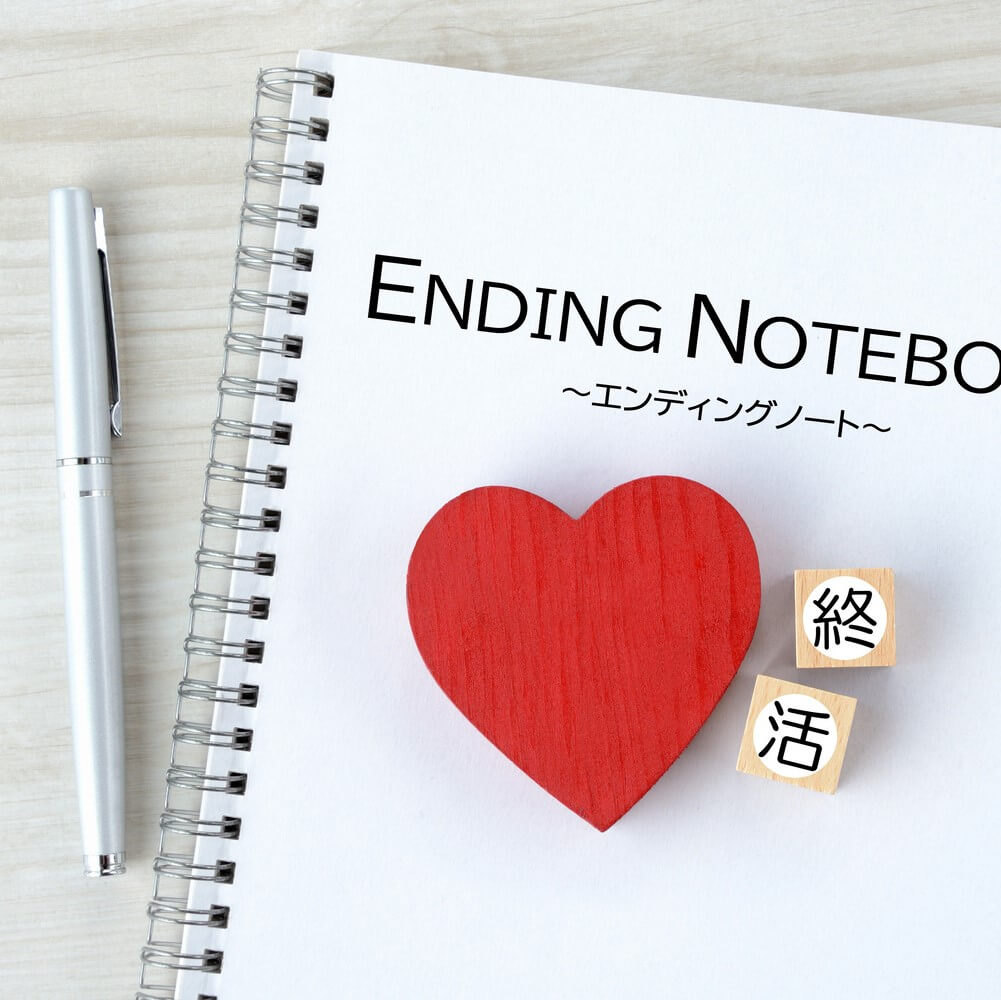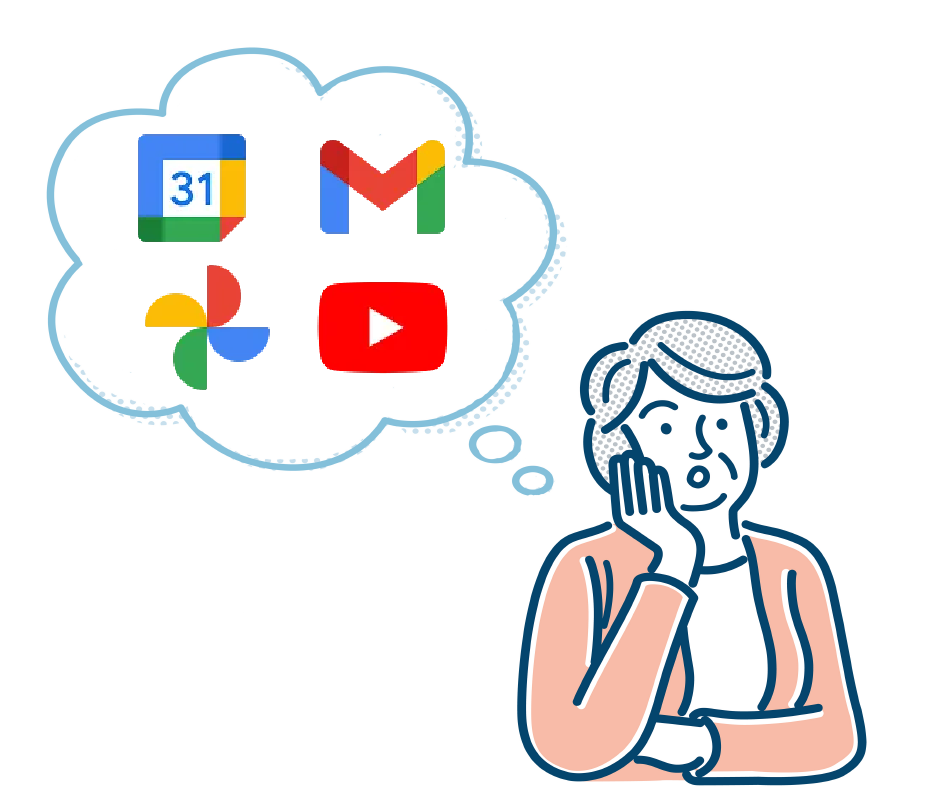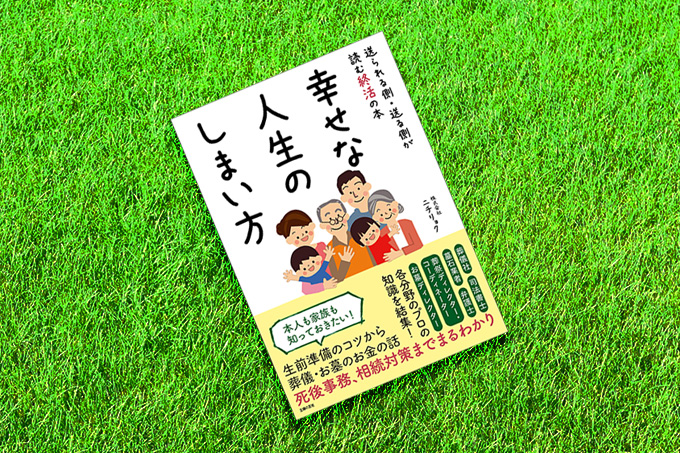【55歳からの終活】日々の暮らし・医療・介護・葬儀・お墓・相続…お金の不安を「安心」に変える4つのステップ

55歳を過ぎ、子育てもひと段落。ふと立ち止まったとき、これからの人生、そして「老後」について考えるようになり、漠然とした不安を抱えている方はいらっしゃいませんか。
人生の棚卸しである「終活」は、この漠然としたお金の不安を解消するための、最も効果的な手段の一つです。
終活とは、決して人生の終わりを準備するだけの暗い作業ではありません。
むしろ、これからの人生を自分らしく、心穏やかに生きるための「道しるべ」を作る、前向きな活動です。
この記事では、終活を通じてお金の不安を「見える化」し、具体的な「安心」に変えていくための4つのステップを、わかりやすく解説していきます。
一緒に、未来への不安を解消する第一歩を踏み出しましょう。
1. 終活の第一歩は「お金の見える化」から
お金に対する不安の最大の原因は、その正体が「見えない」ことにあります。
収入、支出、資産、負債…これらが一体いくらあり、将来どのように変化していくのかが不明瞭だからこそ、私たちは過度に心配してしまうのです。
終活におけるお金の整理とは、この見えないものに光を当て、「見える化」する作業に他なりません。 まずは、以下の3つのステップで、ご自身の財産を徹底的に洗い出してみましょう。
- 財産の棚卸し:プラスとマイナスの資産をリストアップ
まずは、現在ご自身が所有しているすべての財産を一覧にしてみましょう。
エンディングノートや市販の財産目録、あるいは普通のノートでも構いません。
頭の中だけで考えず、必ず書き出すことが重要です。
プラスの財産(資産)
- 預貯金:どの銀行のどの支店に、普通預金・定期預金がいくらあるか。
- 有価証券:株式、投資信託、国債など。証券会社の情報も忘れずに。
- 保険:生命保険、医療保険、個人年金保険など。死亡保険金額や解約返戻金の額も確認しましょう。
- 不動産:自宅の土地・建物、マンション、所有している他の土地など。固定資産税の納税通知書が参考になります。
- その他:自動車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権など、価値のあるもの。
マイナスの財産(負債)
- ローン:住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど。残高と完済予定時期を明記します。
- その他:個人間の借入れなど。
この作業を行うだけで、「自分にはこれだけの資産があったのか」という安心感や、「ローンの返済を優先しよう」といった具体的な目標が見えてきます。
- 老後の支出予測:これからのお金の使い方を考える
次に、将来の支出を予測します。まずは現在の家計簿をもとに、1ヶ月の生活費を把握しましょう。その上で、老後の生活で支出がどう変化するかを考えます。
- 減る可能性のある支出:子どもの教育費、住宅ローン(完済後)、仕事上の付き合いの費用、生命保険料(払込完了後)など。
- 増える可能性のある支出:医療費、介護費、趣味や旅行の費用、孫へのお祝いやお小遣い、住まいのリフォーム費用など。
「退職後は夫婦で旅行を楽しみたい」「趣味のガーデニングにもっと時間をかけたい」など、ご自身の理想の暮らしを思い描きながら、具体的な金額を予測していくことが大切です。
- ライフプラン表の作成:未来の家計をシミュレーション
財産の棚卸しと支出予測ができたら、それらを時系列でまとめた「ライフプラン表(キャッシュフロー表)」を作成してみましょう。
横軸に年齢(例:55歳〜100歳)、縦軸に「収入(給与、年金など)」「支出(生活費、特別な支出など)」「年間収支」「貯蓄残高」の項目を設けます。
この表を作成することで、「何歳の時点で貯蓄がいくらになるか」「どのタイミングで資金が不足しそうか」が一目瞭然となります。
漠然としていた「老後2,000万円」という数字が、自分自身の具体的な目標額として見えてくるはずです。
もし資金が不足しそうなら、「65歳まで働く」「保険を見直す」「資産運用を検討する」など、今から打てる対策を考えるきっかけになります。
金融庁の「ライフプランシミュレーター」を利用すると手軽に将来の収支の見込みが分かります。
2. 将来かかる費用を具体的に把握する
ライフプラン表を作る上で、特に気になるのが「老後の生活費」「医療・介護費」「葬儀費用」ではないでしょうか。
ここでは、公的なデータに基づいた平均的な数値を参考に、ご自身のケースを考えてみましょう。
- 老後の生活費
- 総務省の家計調査(2022年)によると、高齢無職世帯の1ヶ月の平均的な支出は、夫婦世帯で約26.8万円、単身世帯で約15.5万円です。
これはあくまで平均であり、持ち家か賃貸か、都市部か地方かによっても大きく異なります。
また、「ゆとりある老後生活」を送るためには、この金額に加えて月々10万〜15万円程度の上乗せが必要という調査結果もあります。
ご自身の理想の生活水準と照らし合わせ、目標額を設定しましょう。 - 医療・介護費
- 病気や介護への備えは、多くの方が不安に感じる点です。
- 医療費:日本の公的医療保険は非常に手厚く、医療費の自己負担は原則から3割です。さらに、1ヶ月の医療費が高額になった場合でも自己負担額に上限が設けられている「高額療養費制度」があります。過度に恐れる必要はありませんが、先進医療など保険適用外の治療には別途備えが必要です。
- 介護費:生命保険文化センターの「2024年度 生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」によると、介護にかかる費用は、住宅改修や介護ベッド購入などの一時的な費用が平均47.2万円、月々の在宅・施設サービス利用料などが平均9万円かかるとされています。また、平均的な介護期間は約4年7ヶ月です。公的介護保険で費用の多くはカバーされますが、自己負担分(原則1〜3割)や保険適用外のサービス費用は自身で準備する必要があります。
- 自分のためのお葬式費用
- 子どもたちに迷惑をかけたくない、という思いから葬儀費用を気にされる方も多いでしょう。葬儀の形式によって費用は大きく異なります。
- 一般葬:150万円-
- 家族葬:80万程度-
- 直葬(火葬式):20万-40万円程度
ご自身がどのような形で見送られたいかを考え、その費用を準備しておくことも、家族への大きな思いやりです。
費用の準備には、現金や預貯金のほか、保険、葬儀信託等を利用することもできます。
葬儀保険については、株式会社ニチリョクでの取り扱いがあります(お問い合わせ:お客様相談室 フリーダイヤル0120-300-100)。
3. 「争族」を避けるための相続の整理
お金の終活は、ご自身のためだけではありません。
残される大切な家族が、お金のことで揉める「争族」に巻き込まれないように準備することも、重要な目的です。
「財産が少ないから大丈夫」「家族の仲が良いから問題ない」といった思い込みが、かえってトラブルの原因になることも少なくありません。
- 遺言:故人様からの最後のメッセージ
- 、ご自身の意思を法的に実現させ、遺産分割協議の手間を省き、家族間の争いを未然に防ぐための最も有効な手段です。特に「配偶者にすべての財産を残したい」「お世話になった長男の嫁にも財産を分けたい」といった希望がある場合は、必ず作成しましょう。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと作成します。費用はかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、最も確実で安心な方法です。
- 自筆証書遺言:全文を自筆で書く遺言です。手軽ですが、要件を満たさないと無効になるリスクがあります。2020年からは法務局で保管してもらえる制度も始まり、利便性が向上しました。
- 家族信託の活用:認知症による資産凍結に備える
- 近年、認知症などによる判断能力の低下で、銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなったり、不動産が売却できなくなったりする「資産凍結」が社会問題になっています。
このリスクに備える有効な手段が「家族信託」です。
元気なうちに、ご自身の財産を信頼できる家族(子どもなど)に託し、自分のため(生活費や介護費)に使ってもらう契約を結びます。
成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、注目されています。 - 生前贈与の活用:感謝を形にする
- 相続税対策として、また、生きているうちに子どもや孫に感謝を伝え、喜ぶ顔を見るために「生前贈与」を活用する方法もあります。
年間110万円までの贈与なら贈与税がかからない「暦年贈与」が基本ですが、2024年からの制度改正でルールが少し複雑になりました。
専門的な知識が必要なため、実行する際は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
4. ひとりで悩まない!専門家への相談という選択肢
ここまで読んで、「やはり自分だけでは難しい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
その感覚は、まったく正しいものです。
お金や法律のことは複雑で、専門家の知識を借りるのが最も賢明な選択です。専門家に相談することは、時間と労力を節約し、何より確実な安心を得るための近道です。
- ファイナンシャル・プランナー(FP):ライフプラン表の作成、家計や保険の見直し、資産運用など、お金に関する幅広い相談に乗ってくれるパートナーです。
- 税理士:相続税のシミュレーションや生前贈与、確定申告など、税金に関する的確なアドバイスをくれます。
- 弁護士・司法書士:遺言書の作成や家族信託、不動産の相続登記など、法的な手続きの専門家です。
いきなり専門家を訪ねるのはハードルが高いと感じる方は、まずは終活について漠然とした不安や悩み、知りたいことについて相談できるところに相談してみましょう。
株式会社ニチリョクは、終活をトータルにサポートする体制を用意しています。
また、相続対策や遺言作成等法律家のサポートが必要な場合には、経験豊富な専門家をご紹介いたします。
まずは気軽にお客様相談室(フリーダイヤル0120-300-100)へお電話するところから始めてみましょう。
5. まとめ:不安の正体を知れば、未来はもっと明るくなる
55歳からの人生は、まだまだ長く、可能性に満ちています。
しかし、お金の不安という重石が心にあると、その一歩を踏み出すのをためらってしまいます。
今回ご紹介したように、-終活を通じてご自身の財産や将来の収支を「見える化」することで、漠然とした不安は「いつまでに、何を、いくら準備すればよいか」という具体的な課題に変わります。
課題が明確になれば、あとは一つひとつ対策を講じていくだけです。
ライフプラン表を作れば、これからの人生で使えるお金がわかり、安心して趣味や旅行の計画を立てられるようになります。遺言書を作成すれば、家族への思いやりを形にできます。 終活は、未来を縛るものではなく、むしろ未来をより自由に、豊かに生きるための準備です。
この記事をきっかけに、まずはご自宅の通帳や保険証券を一度、机の上に並べてみることから始めてみませんか。
その小さな一歩が、これからの数十年の人生を、晴れやかな「安心」で満たすための、確かな第一歩となるはずです。