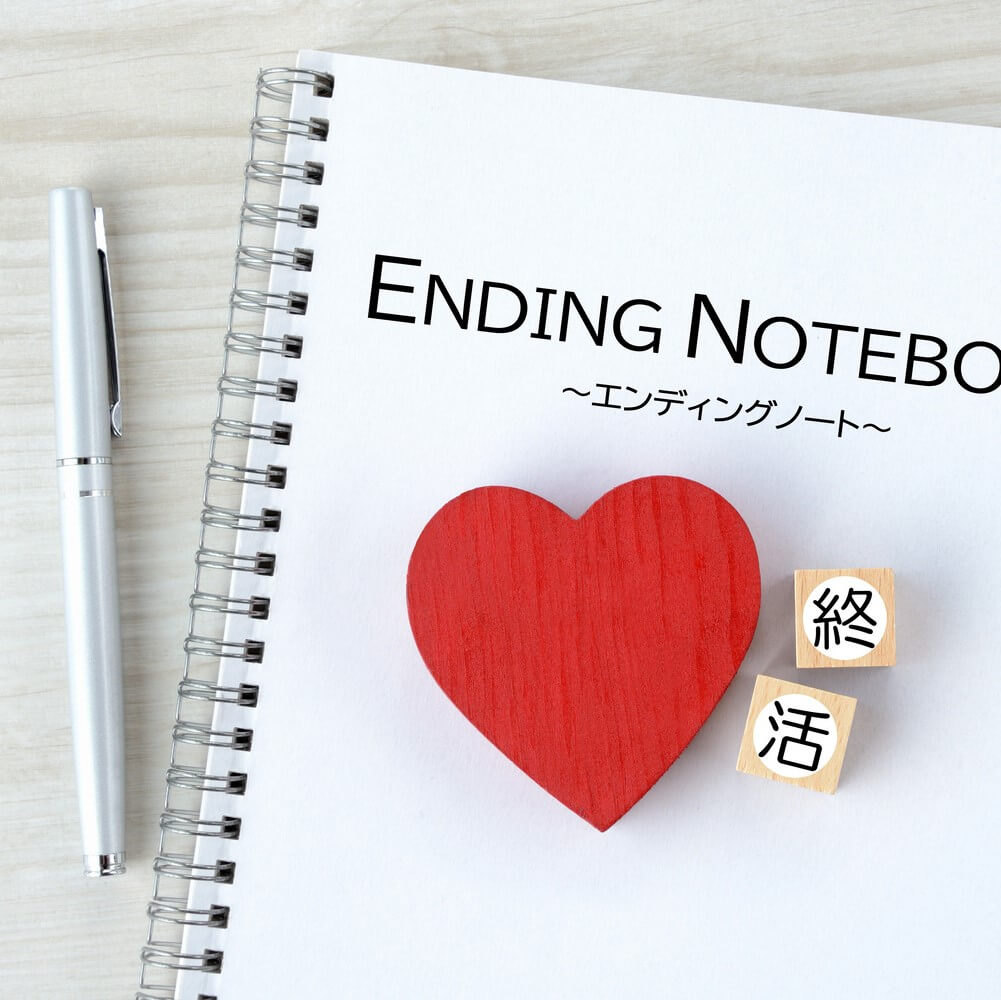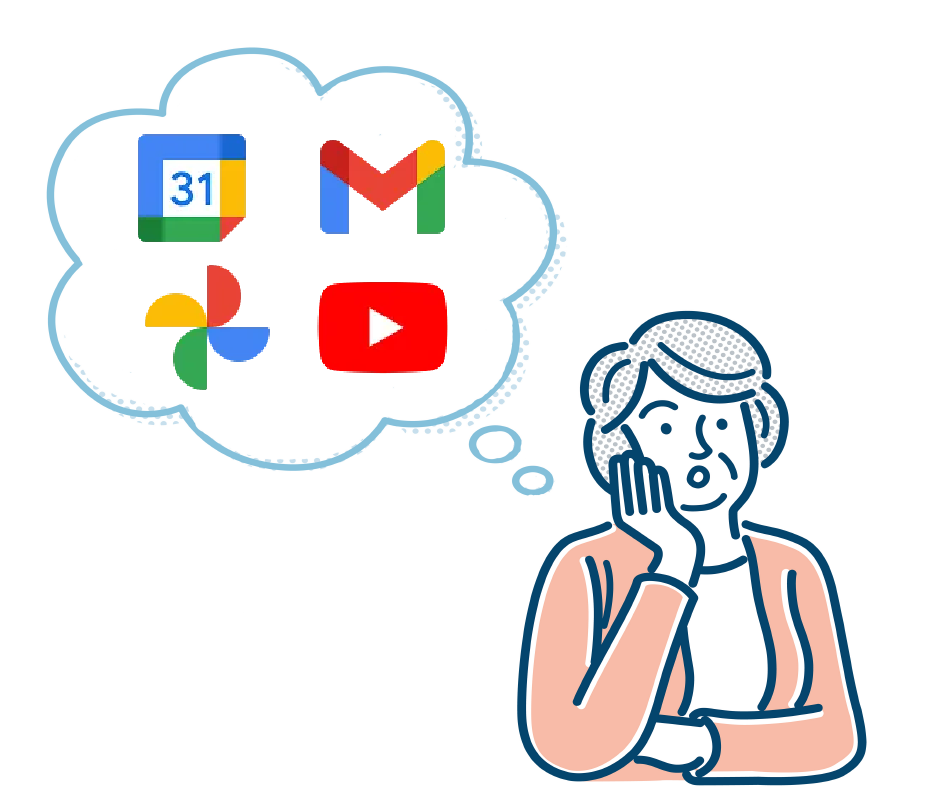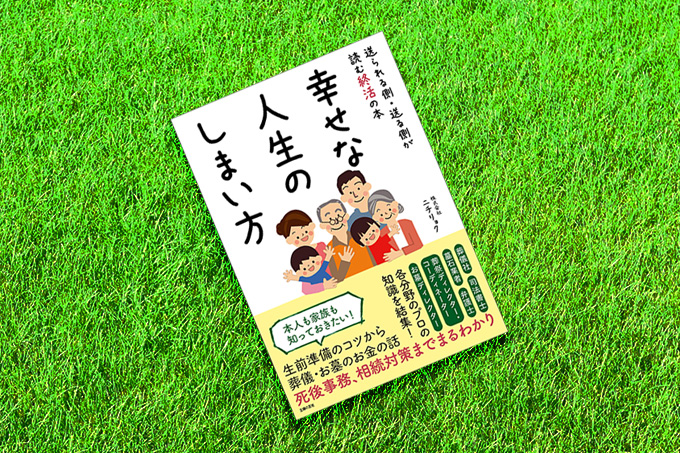願いを叶え、家族に安心を残すエンディングノートと遺言の違い、その賢い使い分けを徹底解説
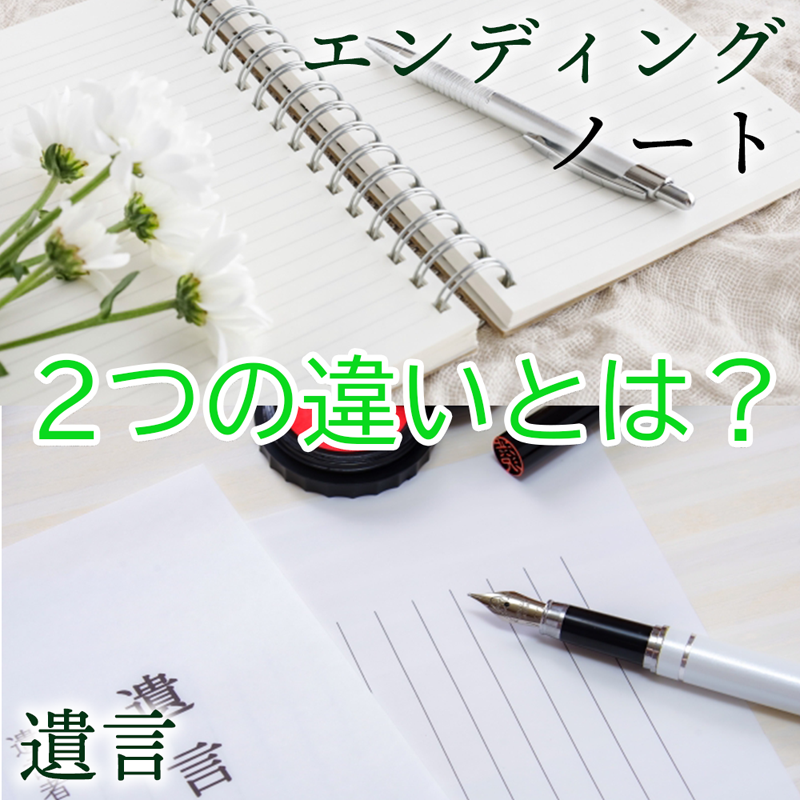
「お父さん、これどうするって言ってた?」
延命治療をどうするか、葬儀はどうするか、お墓は?相続は?
一つ一つの決断に迷い、兄弟で意見が割れ、後悔や不信が残る――。
「自分の時には、家族にこんな思いをさせたくない」と思う方もいらっしゃることでしょう。
そんな方に知っていただきたいのが、エンディングノートと遺言書の違いです。
この記事では、エンディングノートでできること・できないこと、遺言でしかできないことを明確にし、安心して人生を締めくくる準備の第一歩をご案内します。
「エンディングノート」とは?
エンディングノートとは、ご自身の人生の終末期や死後に備えて、ご自身の情報や希望、そして大切な人へのメッセージを書き記しておくノートのことです。 「エンディング」という言葉から、「死の準備」という少し暗いイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私たちはエンディングノートを「これからの人生を、より豊かに、自分らしく生きるためのライフプランノート」だと考えています。 自分の人生を振り返り、大切な思い出や感謝の気持ちを綴る。やり残したことや、これから挑戦したいことをリストアップする。そうすることで、残りの人生の目標が明確になり、一日一日をより大切に過ごすきっかけにもなるのです。
「エンディングノート」にできること
エンディングノートには決まった形式はなく、自由な内容を書き記すことができます。主に、以下のような項目を記録しておくことで、もしもの時に家族の助けとなります。
- 1. 自分自身に関する情報(自分史)
-
- 氏名、生年月日、本籍地などの基本情報
- 学歴、職歴、資格など、あなたの歩んできた道のり
- 思い出の場所、好きだった音楽や映画、尊敬する人など、あなたの人柄が伝わる情報
- 大切な友人や知人の連絡先リスト
- 2. 希望を伝えること(意思表示)
-
- 医療について:延命治療を希望するかどうか、病名や余命の告知を希望するかどうかなど、デリケートな問題を自分の言葉で伝えられます。
- 介護について:もし介護が必要になった場合、自宅で過ごしたいか、施設に入りたいか。誰に介護をお願いしたいかなどの希望。
- 葬儀について:希望する葬儀の形式(家族葬、一般葬など)、宗教・宗派、呼んでほしい人のリスト、遺影に使ってほしい写真、好きだったお花など。
- お墓について:先祖代々のお墓に入るのか、新しく用意するのか。あるいは、樹木葬や散骨など、希望の埋葬方法。
- 3. 必要な情報を残すこと(引継ぎ)
-
- 財産リスト:預貯金(銀行名・支店名)、有価証券(証券会社)、生命保険(保険会社)、不動産、貴金属、ローンや借入金などの一覧。※あくまで「どこに何があるか」を知らせるためのリストです。
- デジタル遺品:パソコンやスマートフォンのロック解除方法、SNSアカウント、ネット銀行や有料サービスのID・パスワードの保管場所など。これらは本人でなければ確認が非常に困難です。
- その他:大切なペットの世話を誰にお願いしたいか、趣味のコレクションをどうしてほしいかなど。
これらの情報を書き残しておくだけで、残されたご家族が迷ったり、手続きで困ったりする負担を劇的に減らすことができるのです。
【重要】知っておきたい!エンディングノートの「できないこと」
ここまでエンディングノートのメリットをお伝えしてきましたが、絶対に知っておかなければならない、非常に重要なポイントがあります。
それは、エンディングノートには「法的効力」がないということです。
どういうことでしょうか?
例えば、あなたがエンディングノートに「私の全財産は、最後まで介護をしてくれた長男に相続させる」と書いたとします。
しかし、他のご兄弟(相続人)が法律で定められた相続分(法定相続分)を主張した場合、エンディングノートの記述は無力です。
あなたの希望とは裏腹に、法律に従って財産が分けられることになり、かえって家族間のトラブル、いわゆる「争族」の火種になりかねません。
また、「葬儀は質素に」と書いても、ご家族が「盛大に送りたい」と判断すれば、その意思が優先される可能性があります。
エンディングノートは、あくまで「家族へのお願い・希望を伝える手紙」です。
あなたの想いを伝えるラブレターにはなりますが、法的な強制力を持つ契約書ではない、と覚えておいてください。
法的効力がある「遺言」だからできること
エンディングノートの弱点である「法的な効力」を持つもの、それが「遺言(ゆいごん・いごん)」です。
遺言は、民法という法律で定められたルールに則って作成することで、あなたの最終意思を法的に実現させることができます。
遺言でしかできない、代表的なことをご紹介します。
- 財産の分配を法的に指定できる
- 「妻に自宅不動産を」「長男に預貯金を」など、誰にどの財産を渡すかを具体的に指定できます。これが最も大きな役割であり、相続トラブルを防ぐ最大の武器となります。
- 相続人以外の人に財産を渡せる(遺贈)
- 長年連れ添った内縁の妻(夫)、お世話になったご友人、母校やNPO法人への寄付など、法律上の相続人ではない個人や団体にも、あなたの財産を渡すことができます。
- 子の認知や、未成年の子の後見人指定
- 婚姻関係にない男女間の子供を自分の子として認めたり、万が一の時に未成年の子供の親代わりとなる後見人を指定したりすることも、遺言によってのみ可能です。
上記のような願いのある方は、その実現のために遺言を作成しましょう。
【一目でわかる】エンディングノートと遺言の違い
両者の違いを、表で比較してみましょう。
| 項目 | エンディングノート | 遺言 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 目的 | 想いや希望、情報を伝える | 法的な最終意思の表示 |
| 記載内容 | 自由(メッセージ、希望など) | 法律で定められた事項(財産分与など) |
| 形式 | 自由(市販品、自作ノートOK) | 厳格(自筆証書、公正証書など) |
| 作成の手軽さ | 手軽に始められる | 専門知識が必要な場合も |
| 費用 | 無料~数千円程度 | 専門家に依頼すると数万円~ |
結論:理想の形は「エンディングノート」と「遺言」の二刀流
ここまで読んで、あなたはどう感じましたか?
「エンディングノートは手軽だけど、大事なことは決められない」「遺言は確実だけど、なんだか難しそう…」
その通りです。だからこそ、私たちは「エンディングノート」と「遺言」の両方を用意する『二刀流』をおすすめします。
日々の想いや細かな希望、各種情報の引継ぎは「エンディングノート」に自由に書き記す。
そして、財産の分配など、法的な裏付けが必要な最も重要な事柄は「遺言」で確実に残す。
この二つを組み合わせることで、あなたの想いをほぼ完璧に、そしてスムーズにご家族へ繋ぐことができるのです。
- ステップ1:まずは気軽にエンディングノートから始めよう
- 「さあ、準備をしよう!」と思っても、いきなり遺言となるとハードルが高いかもしれません。
まずは、エンディングノートから始めてみませんか?
完璧を目指す必要はありません。
「自分のプロフィール」や「好きな音楽リスト」など、楽しく書けるページからで大丈夫です。
まずは1ページ埋めてみることが、未来の安心への大きな一歩になります。 - ステップ2:重要な財産のことは遺言で確実に
- エンディングノートを書き進める中で、「この財産だけは、この人に」という明確な想いが出てきたら、それが遺言を作成するタイミングです。
遺言は法律で定められた厳格な形式があり、一つでも不備があると無効になってしまう可能性があります。
大切な想いを無駄にしないためにも、作成は専門家へ相談するのが最も確実で安心な方法です。
賢く、手軽に始めるための具体的なアクションプラン
「二刀流が良いのはわかったけど、具体的にどうすれば…?」
そんなあなたのための、具体的なアクションプランをご提案します。
書店にはたくさんのエンディングノートがありますが、「どれを選べばいいかわからない」「必要な項目が網羅されているか不安」というお声をよくお聞きします。
そんな方におすすめなのが、私たちニチリョクの会員制度「あおい倶楽部」です。 もしもの時の備えをトータルでサポートするこの倶楽部にご入会いただくと、特典として、長年お客様の声をお聞きしてきた私たちが作ったオリジナルのエンディングノート『家族と話す令和のエンディングノート』を無料で進呈いたします。
自分史から財産リスト、葬儀の希望まで、これ一冊で必要な項目がしっかりと網羅されており、書き進めるだけで自然と備えができます。
「あおい倶楽部」は入会金無料なうえ、月々の会費などは一切かかりません。
加えて、もしもの時の葬儀費用やお墓の建墓費用が割引になったり、遺言作成や相続税対策などの専門家の相談が無料でできるなど、ご家族の金銭的な負担を軽くする特典もございます。終活の第一歩として、これ以上ない選択です。
「遺言を書きたいけど、誰に相談すればいいの?」
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言は、全て無効となります。
「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。
そのため、法的要件を満たした遺言を作成する場合、自筆証書遺言を選んだとしても、専門家に相談しながら進めた方が、安心です。
「でも、相談できる専門家に心当たりがない」という方もいらっしゃることでしょう。
そのような場合は、ニチリョクのように、終活をトータルでサポートできる企業に相談すると、遺言や相続に詳しい経験豊富な専門家を紹介してもらえます。
「あおい倶楽部」会員であれば、相談は無料です。
「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
人生100年時代。50代、60代、今では70代の方でも「まだまだこれから」と思われているのではないでしょうか。
人生の節目に一度立ち止まり、ご自身の想いと向き合う時間は、これからの人生をより豊かにし、そして未来の家族に大きな安心を贈ることにも繋がります。
エンディングノートで想いを伝え、遺言でそれを法的に守る。
この賢い「二刀流」の備えを始めてみませんか?
まずはその第一歩として、詳細がわかる「あおい倶楽部」の資料請求から始めてみませんか?
あなたの「これから」を、私たちが全力で応援します。